





|
◆味土野(みどの)
所在:京丹後市弥栄町須川(やさかちょうすがわ)
大字須川の南部にある。 ※ 新聞記事より 以下は資料『味土野誌』より。 主な生業は田(ほとんど小作農)・養蚕(多くの家で行っていた)・焼畑(そば・小豆など)
また『味土野誌』に掲載されている新聞記事によると、牛飼いをする家もあったよう。冬になると積雪で集落は孤立し、記事が書かれた昭和61年当時でも除雪車が入らず、自動車が通れるようになるのは3月になってから。麓からかんじきを履いた郵便配達員が登ってきてくれていたという。
論文「丹後地方における廃村の多発現象と立地環境との関係」によると、明治初期44戸、平成2年3戸。
|
|||||||||||||||||||||
 写真1 碑 |
 写真2 集落風景 |
||||||||||||||||||||
 写真3 家屋 |
 写真4 学校跡の施設 |
||||||||||||||||||||
 写真5 屋敷跡 |
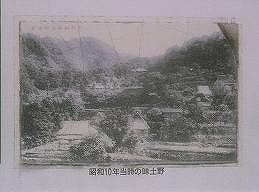 写真6 往時の集落風景(案内板より) |
||||||||||||||||||||
 写真7 碑 |
 写真8 墓地 |
||||||||||||||||||||
 写真9 「味土野古寺跡」 |
 写真10 「三宝荒神跡」 |
||||||||||||||||||||
 写真11 「堂山、七堂伽藍之跡」 | |||||||||||||||||||||